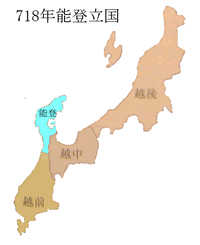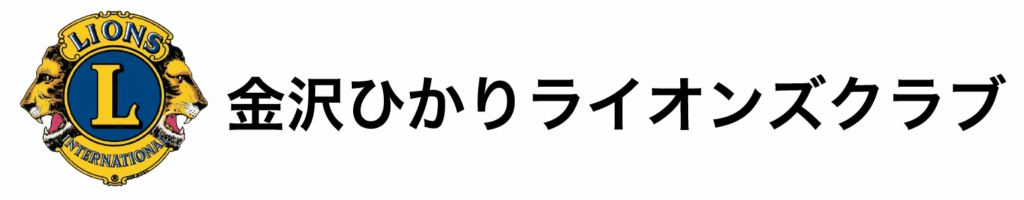大和朝廷が近畿地方を中心に勢力を伸ばしていた頃、越といわれた 金沢平野にも道君(みちのきみ)という豪族が活躍していた。高句麗の使者が日本海で遭難し この地に上陸したさい、彼らは道君に大和の天皇と偽られ貢ぎ物を横領された。これを知った 南加賀の豪族江沼氏が大和朝廷に訴えたので道君が厳しく問い詰められたと『日本書紀』 に記されている。
7世紀半ば、天智天皇宮人の中に越道君伊羅都売(こしのみちのきみいらつめ) という名があり、 これが道君の娘です。宮人となった伊羅都売は、650年に白壁王を生みます。 後に光仁天皇となった人です。
道君一族は、8世紀になると金沢平野全域を手に入れ、同時に白山信仰の権力を持ち、私寺として末松廃寺 (野々市町末松)を建立した。 885年その一族の道今古の名を最後に歴史から姿を消しました。
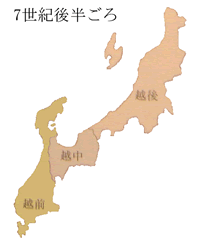
平城京に都を移す(710年)
越前の国から分かれて能登国ができる。能登国を越中の国にあわせる。
大伴家持が越中の国司になり能登をまわる。
当時は、海路がよく使われていて、陸上の交通路はまだ開けておらず、数多くの苦しみがあったようだ。
土地と人民の様子を調べるために、能登地方へ見てまわった歌人家持がよんだ歌が『万葉集』にのっている。
「之乎路からただ越えくれば羽咋の海朝なぎしたり船かじもがも」
(志雄から道をまっすぐに越えてくると、羽咋の海が朝なぎして静かである。船とかじがほしいものだ)
「香島より熊木をさしてこぐ船のかじとる間なくやこし思ほゆ」
( 香島から熊木をさしてこぐ船の、かじの休む間もないように、たえ間なく都のことが思われる)
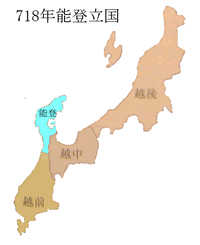
桓武天皇が政治の立て直しをはかり、平安京に都を移してまもなく加賀国ができました。
823年越前国から江沼郡・加賀郡をさいて加賀国が誕生しました。半年後に江沼郡の北半分を能美郡、 加賀郡の南半分を分けて石川郡がたてられました。国府は能美郡に設置したといわれています。
当時の加賀国と能登国は、今の加賀・能登とは、異なった発展をしていました。能登国には大きな港があり、 早くから大陸文化に触れることができました。日本海の対岸に渤海(ぼっかい)という国が建国され、 朝廷は能登の福良泊(福良港)に使節の受け入れを積極的に行っていました。